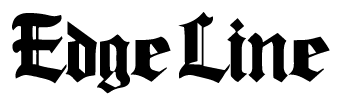俳優・仲野太賀(27)、大島優子(31)、若葉竜也(31)が3日、東京・ユーロライブで映画『生きちゃった』(脚本・監督・プロデューサー:石井裕也/配給:フィルムランド)初日舞台あいさつを石井監督(37)とともに開いた。
本作は、幼馴染みの山田厚久(仲野)と奈津美(大島)、そして武田(若葉)の3人の幼馴染の物語。いつも一緒に青春を過ごしていた3人。30歳になった現在、厚久と奈津美は結婚しており、5歳の娘がいる。平凡だがそれなりの生活を送っていたある日……。厚久が奈津美の浮気を知ってしまう。あまりにも突然のことで、厚久は怒ることもできなければ悲しむこともできない。感情に蓋をすることしかできなかった。その日を境に厚久と奈津美、武田の関係は歪んでいき、物語は衝撃的な展開へと向かっていく……。
仲野は昨年撮影しているときに、新型コロナウイルスが生活に影響する世の中になることは想像つかなかったと感慨深げで、大島も、「こういう状況の中で、自分たちが生かされたのか……生きようとしているのか……生きちゃったという言葉がしっくりくるなと思って」と、本作タイトルと世情とマッチしていたといい「こうやって初日を迎えられたことが嬉しいです。これが全国に届けられることを噛み締めています」と、笑みを浮かべていた。
石井監督が「すさまじい、言葉にならないラストシーンを作ってみたかったというのが僕くの中でのテーマでした」と、並々ならぬ熱量を込めた本作だけに、脚本を読んだとき仲野は、「しびれました」と切り出すと、「石井監督が3日間で書いた脚本の熱量と切実な思いだったり、作家が本当に思っていることが並んでいて、脚本の力強さにしびれましたし、これが僕が演じることの意味として、絶対に言い訳できない状況になるんじゃないかなって思いました。自信を持って堂々とここにいられるというか。全部出しちゃっているので、とても気合を入れて臨みました」と、石井監督の熱量を追い込まれながらも受けきったと自信を見せる。
大島も「脚本を読んでいるときは小説を読んでいるようでした。台本のト書きってその役柄の説明とか感情の後付けの補足、情景の補足だったりするんですけど、そのト書きが大切な一行ずつになっているんです。ト書きの一行で試されているような気持ちになるんです。たとえば奈津美は『仏のようにいろんな表情を出している』と、これをどう演じるんだろうって思って。試されているなと思って。だからこそ、私なりの奈津美はがどうでき上がっていくんだろうと読んだときに高揚しました」と、演じ甲斐がたっぷりとあった様子を窺わせる。
若葉は「部屋で1人で読んでいたんですけど、パソコンで書かれているんですけど、手書きで書いているようでした。普段コンタクトをしているんですけど、そういったものを通すと見えるものが違うので、これはメガネをかけて読む台本じゃないと思って裸眼で読みました。それで、最後のシーンを観て、これどうしようと気持ちもありました」と、熱量におののいた部分もあったよう。
それでも若葉は「自分の想像していない顔がスクリーンに映っていて、これは人に見せられる顔じゃないと思って」というほどむき出しの表情を見せたといい、「全部捨てて演じました。その姿を映画館で目の当たりにしてほしいと思います」と、アピールしていた。
そんな作品の熱量を“試されている”をキーワードに語る4人だったが、仲野は「この映画は大きなことをいうと運命の映画だと思うんです。『生きちゃった』という言葉、生きているということ、誰しも自分自身では抗うことができない大きな流れがあってそこに巻き込まれて人たちの話だと思っていて、3人が出会ったことがすべてだったに尽きると思います」と、作品の本質を語っていた。
映画『生きちゃった』は渋谷・ユーロスペースにてR+15で上映中!なお、10月以降に『All the Things We Never Said』という英語タイトルで中国および香港、台湾、マカオなど、世界各国の劇場で公開を予定している。