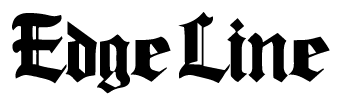【前編JAM Project初ドキュメンタリー映画のタイトルに込めた監督の思い!影山ヒロノブ「俺たちの内面をすごく探ってた」や奥井雅美「監督は預言者!」?より】
影山:(きただに)ひろしと一緒なんですけど、自分も10代のときにやっていたバンドの『レイジー』が(1981年5月に)解散してその後、5年くらいめっちゃめちゃ低迷していたんですよ。自分の人生の中で。もう、レコード会社クビになるわ、事務所クビになるわ、バンドを解散して最初はホールとかでやったんですけど、もう2年もしない間に、演奏できる場所はどんどん小さくなっていって。でも、それまでできなかった曲を自分で書くぞ!詩も自分で書くぞ!あとは年間150本くらい頑張って、ライブやるぞと根性だけでやっているときに、24歳か25歳のころかな、当時の日本コロムビアのアニメセクションの木村(英俊)ディレクターから、「来年の戦隊シリーズの歌を影山くんやってくれないか」って言ってもらえたのが、なんだろう……何年ぶりかに世間が自分を見てくれたというか。そんなオファーも全然なかったんで。そこから今日まで途切れてないのが自分の人生なんですよね。「自分を暗闇から救ってくれた!!」ぐらいな。
ファンの人たちもその当時、影山ヒロノブのスタイルみたいなものへすごくウエルカムな反応を示してくれて。自分がいいものを残して、自分を救ってくれた業界と、救ってくれたファンの人たちに恩返しをしたいというところからのスタートなんですよね。
そこからもう35年が過ぎて、いまやっぱり思うのは、アニソンシンガーって、作品がセンターに座っているとしたら、その周りのチームの一員になれる覚悟があってやっているのかどうかが、アニソン魂だと思うんですよ。自分が何で歌を歌って、アニソンを作ってレコーディングして、1番喜びを感じるかっていうのを振り返ったときに、まずやっぱり、作った作品(楽曲)をプロデューサーとかが聴くじゃないですか。そのときに、「うわー、今回のやつ、もう最高ですよね!もう俺たちが伝えたいことがこの曲に入ってますよ!」と言ってくれたら、めっちゃアガります。これこそが俺たちの仕事なんだなと、まず思います。そして、その次にその曲が世の中にリリースされたときに、ネットなどで、番組やヒーロー、原作ファンの人たちが、「神!」みたいに言ってくれたら、そこで俺たちは、「ああ、良い仕事に参加できてよかったな」って心から思えるんですよね。それがアニソンマンの立ち位置であり格好いいところだと思うんですよ。
チームの一員として、たとえば声優さんとか、アニメを実際に作っている人たちや音響を作っている人たちが、みんな同格で並んでいるなかで自分たちも、チームの一員というのが、アニソンシンガーの男っぷり、女っぷりだと思うんですよ。だから、アニソンって音楽性ではないので、アニソンシンガーにただなりたいってなるのはちょっと変だなと思うんですけど、「遠藤さんの歌が死ぬほど好きで、あんなふうに歌えるようになりたい!」とか「奥井ちゃんみたいな歌を歌えるようになりたい!」とかだったらもう全然オッケーだと思います。それは俺たちが憧れた、70年代のロックスターとまったく一緒だと思います。それを卑下する必要もないし。ただ、アニソンシンガーになりたいんだったら、そういう自分がスターになって、アニソンの世界はタイアップがおいしいからスターになって夢を叶えました!ということではなく、自分たちの立ち位置を職業的に誇れるような気持ちを持ったミュージシャンになってもらいたいですよね。それがアニソンのスピリットなんじゃないかなと思います。
奥井:私が子供のころってアニソンシンガーっていうくくりもなくて、漫画の歌を歌っている人。アニメという言葉もなくて、堀江美都子さんの歌っていた『キャンディ・キャンディ』を買っていたり。で、自分はバックコーラスのお仕事をやっていたときに、ちょうどキングレコードさんから林原めぐみさんの仮歌を歌うお仕事をしていたんです。それとレコーディングのコーラスをしていたんです。それで歌っているのを聴いた、レコード会社の方に、「1回歌ってみない?」って言われて、モノマネつきで。記念になるからというくらいの感じで。自分も子供のときに、昔のレコードの17センチ45回転の漫画の主題歌のCDをいっぱい持っていたんですよ。割と漫画の曲を聴いて育っているし「あっ、ああいう感じの漫画とかの曲なのかな?」って。当時、レイジーのファンであったにもかかわらず、アニソンのこととかも分からなかったので、そういうのを専門にお仕事にしている方々がいるというのも堀江さんしか分からなかったんです。それで、男性だったらささき(いさお)さんと、アニキ(水木一郎)しか分からなかったんですけど、アニソンシンガーというより、ただ、バイト感覚でアニメの曲を歌ったんです。最初の頃は堀江さんみたいに綺麗に正統派の歌い方をしないといけないのかなと思って、そのように歌ったりしていたんです。でも、歌っているうちに、「好きに作っていいよ」「もう1曲このアニメをやりませんか」みたいな感じで段々お仕事になってきたんです。それで、「えっ、待って」となって、じゃあちょっとJ-POPのテイストを入れてみたらどうだろうかとか、私の場合だと踊れるようなものとか、歌謡ロックが好きだったので、そのテイストを入れたらどうかなというふうに自分たちのチームで作ったりしはじめて。気づくとJAM Projectにも入って、こんなに長くやっている、もうなんか生活の一部になってしまって……“しまって”と言うといけない言葉みたいですけど(苦笑)。
影山:(小声で)嫌だったんだ(笑)。
奥井:嫌じゃないですよ!(笑)。まさかこんなに長くやると思っていなかったし、女なので続けられると思ってなくて。男の人だと年を取って歌っても格好いいけど、女の人で格好良く年を取りながら現役でいるというのはすごく難しいなと思っていて。とくに前に出て歌うというのもあって。そこがいま自分の課題ですけど、自分にとってみれば(JAM Projectは)そういう存在なんです。アニメソングって、兄さん(影山)もすごく熱く語ってくださいましたけど、私が歌詞を書いてみて思ったんですけど、夢や希望などは、自分が書き始めたころは、あんまり歌に乗せて言うのって、こっ恥ずかしくてアニソンぐらいでしか、夢や希望を歌える歌はないんじゃないかなってとくに思っていたんです。だから、それを恥ずかしくなく歌えるのがアニソンの良いところだなと思って。あと自分のポリシーがあるんです。それはひどくネガティブな歌詞というものもあるけれど、ネガティブななかにも最終的にちゃんと1つの光が見えるように、歌詞の中で終わらせるというのを心掛けていて、それはいまもJAMで歌詞を書くときにもそうだし、アニメ作品でも、そういう作品が好きです。
遠藤:アニソンって、ジャンル的にないとか、厳密に言えばあるのかもしれないですけど、僕もアニソンシンガーになりたくて、いまがあるわけじゃなく、兄さん(影山)と同じ事務所に入っていまのレコード会社の社長から「歌ってみないか」というところから始まったし。よく聞かれるのは、アニソンを歌うのと自分のバンドで歌う違いってどこですか、どういう違いで歌われているんですかって。でも、俺、そういうの分けたことないんですよ。もし音楽にジャンルがあっても、俺は歌にジャンルがあると思ってないので。そういう感じで歌ったことはいままでもないし、たぶんこれからもないだろうなって思うし。そういう意味でもアニソンだから、とかいう意味が自分のなかにはなくて。映画の中でも言っているんですけど、俺の主観ですけど、俺がアニソンを歌いはじめたときって、世の中アニソン=ちょっとオタクとか暗いイメージというか悪いイメージの方が多かったんです。だから、今の若い子たちが、「きょう、アニソンのライブに行くんだ」とか、「このアニソンいいんだよ」と、胸を張って言える時代になればいいなと。もし、そこでうちらがアニソンを歌えるんだったら……そういう世界にしていきたいなと思って。自分だと力不足かもしれないけれど、そういう世界になればいいと思って始めたので。今の子たち、たとえばLiSAちゃんとか、アニソンが市民権を得たいまの時代なので、若い子がアニソンシンガーになりたいとか、そういう夢を語ってくれるんだったら、すごく素敵で、うちらもなんか力になれているのなら嬉しいなと思います。
――続けて、影山さんにお伺いします。作品中でアニソンというものへ、「シンガーソングライターが引っ張っていくような時代にしたい。そうしないと真心とかが伝わらない」とおっしゃっていて、実際にアニメソング界の音楽シーンで、シンガーソングライターが担当する方が増えていると思います。アニソンのジャンルも広がりを見せていますが、影山さんが今現在感じていらっしゃるアニソンらしさみたいなものはありますか?
影山:作品中でお話ししたときに思っていたのは、ずっと自分たちも自分たちで手作りしなきゃ、これからはダメだろうなと思っていて、JAM Projectを結成したときにもその思いがあって。それから20年経って、自分たちは手作りすることを一生懸命進めています。そのなかで、たとえば2015年のアニメ『ワンパンマン』のOP『THE HERO!! ~怒れる拳に火をつけろ~』とか、いろんなサウンドを試みて、メロディーなのかラップなのか、騒いでいるのかよく分からないようなことも交えながら、試行錯誤しています。それは、自分たちがシンガーソングライターで、手作りで、自分たちの中から出てきたものと、作品がコラボしているのが理想だと思ったから、そうなんです。それこそ去年の1月1日に出た俺達の20周年記念アルバム(『The Age of Dragon Knights』)で、一緒にやりたいと思っていた、『FLOW』、『GRANRODEO』、『angela』、『ALI PROJECT』とコラボしたんですけど、彼らは自分たちでアニソンを手作りして、自分たちの個性をしっかり維持したままアニソンを作っている方々だと思っているんです。で、さっき遠ちゃん(遠藤)が例に挙げた去年の1番大きなアニソン界のアイコンであるLiSAちゃんは俺たちと同じようなスタイルだと思います。だから、ファンの人も、「この人たちは本音で、心から好きでやっていて、自分たちの内面から出てるんだな」と思っていると思います。それは、もう1番大切なことじゃないかなと思います。愛にあふれてるっていうことだと思います。
――2003年に発表された「SKILL」という楽曲はJAM Projectといえばこの曲という1曲で、発売当時は、ただただ格好よくハーモニーの素晴らしさに酔いしれましたが、いま現在歌い継ぐにあたって歌詞の「♪新たな伝説を 今この手で刻むんだ!!」「♪何度でも立ち上がれ未来が俺を導くかぎり 不死身さ!!」などの歌詞は、当時とは違う意味合いを帯びた曲になっている気がしています。歌っているJAMさんたちにとってこの曲を歌い継いでいくなかで意味合いが変化した部分やエピソードはありますか?
影山:『SKILL』って、いまのメンバーが入った時にやった曲だよね。17、18年くらい歌っているんですよ。その最初の頃、話題になって『SKILL』を多く歌っていたんですけど、ファンの方々も「また『SKILL』なの……?」というときもあったと思います(苦笑)。
きただに:でも、セットリストから外したら外したで、なんか言われるんじゃ……という曲のポジションってあるじゃないですか。
影山:ここにいるみんな、そうだと思います、たとえば(遠藤の持ち歌で有名な)『ガオガイガー』の曲だったり。
遠藤:あんまそれはないですよ(笑)
奥井:私は、いまは行けないですけど、友達とカラオケに行ったときに、なぜか選曲中に出てくるから『SKILL』歌っちゃうんですよ。兄さん(影山)のモノマネをやっちゃうんです(笑)。
遠藤:『SKILL』って、このメンバーになってから初めてレコーディングしたし、このメンバーを1番表せているんだろうなって思っているんです。CDとかって、歌詞を書くまではいろんなことを考えて、こういうことを伝えたいと思うんですけど、CDになったら聴いてくれる人がどう感じようが、180度違うことを感じてもそれは正解だし、どんどん変わっていくものだと思うから。18年経ったら変わるものですよね。なんか俺も、こういう歌詞なんだってあらためて思いながら歌うときもあるし。そう考えるとどんどん変わっていくんだなと思います。
奥井:ライブで『SKILL』を歌っているときにファンの人たちの表情を見たら、すごく楽しそうにしてるし、自分たちが楽しそうに歌うと、ファンの人たちはそれを喜んでくれるんで、こっちが楽しそうに歌っているのが、みんなも幸せになれるのかなって。『SKILL』ってそういうアイテムの1つですね。
きただに:最年長者(の影山)が(曲に合わせて)ぴょんぴょん飛んでますから。本当に楽しそうに飛んでますよ(笑)
影山:還暦過ぎたら、ステージにトランポリン置くから(笑)。歌詞の「♪I can fly!」の部分で飛んで、降りてこなかったりして(笑)
福山:『SKILL』って初めて聴いたときに、いままで歌ったなかで1番構成が難しい曲だなって感じたんです。
4人:(そろってうなずく)
影山:かなり構成が変だよなぁ(苦笑)。
福山:そう、かなり変で(笑)。でも、ファンの方々が間違えずにいま一緒に歌ってくれているのが、不思議でしょうがない時期があったんです。こんな難しい曲、よくみんな覚えられるなって。サビが3回あるんですけど、3回とも入り方が違って、引っ掛けみたいなやつもあって、それにあの釣られないで、ファンのみんなも入ってこれると。
きただに:メンバーも間違うほどなのに、ですよ(笑)。メンバーの間でも「あっ、言っちゃった……」っていうこともあるんです。
福山:そんな複雑な曲が、JAMのスタンダードになっているというか、僕にしてみたらJAMの活動はそこから始まってるんです!
遠藤:もうアンセム(代表曲)だよなぁ。
奥井:うん、そうだね。
きただに:(影山に向かって)でも、『SKILL』を超えることが目標なんですよね。
影山:そう!『SKILL』を超えるような曲を成長した自分たちが作るということが合言葉になっているんだけど、それはまだ未来の仕事になってるかな(苦笑)。あと、最近はみんなひと回りして、みんな結構高いモチベーションで、『SKILL』をやれるように戻ってます。ファンの方たちも割と、『SKILL』にたるみはないよね。
遠藤:それと、コロナ禍で配信でライブをしたんですけど、この曲はお客さんと掛け合いをして一緒に楽しむものとしてできあがっているので、配信だと外したりしてました。やっぱりお客さんと一緒じゃないと成り立たないという部分があるというのを自分らも知ったので、余計、この曲の良さや意味合いが分かった気がします。
奥井:はやくライブやりたいなぁ(笑)
――最後に、今後のJAM Projectさんの夢や野望はありますか?
影山:映画のなかで、自分が何を言いたいのかなって思ったんですけど、奥井ちゃんも先程言ってましたけど、作品の中にはネガティブなシーンもあるんです。そのインタビューに答えている時期は、自分たちがちょっと行き詰まっている感じがあったんですよね。さんざっぱらやってきて、曲を作っても、なんか同じようなことになっちゃうころだったと思うんです。その当時思ってたことはマンネリなんです。でも、映画の最後で、俺たちもっとやるしかないだろうと言ったのは、同じことを見てるけどマンネリじゃなくて、自分たちにしかできないスタイルということなんです。それを、未来に対して、もっと、乱暴なことを言えば、「中途半端にマンネリをやっているからダメなんだぞ俺たちは!」ということを俺は言いたいんです。中途半端じゃなくて、マンネリを通り越して、誰も到達できない、JAMにしかできないスタイルを未来に対して、追い求めるのがこれからのJAMの仕事だと思っています。だから、映画はある意味、それを自分にも確認させてくれました!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■編集後記
インタビュー中、5人へどんな質問をしても、楽しかった体験はもちろん、つらかった体験でも、カラリと笑いながら答えてくれていた姿が印象的だった。その話の最中にも、メンバー同士の明るい掛け合いが始まったり、話が脱線しそうになることもしばしばだったが(笑)。
しかし、そんな姿は、ステージで輝きを放っているときとまったく変わらない関係性を感じさせてくれた。飾らない人柄という言葉があるが、話をしているだけで自然に笑顔になってしまう明るさがJAM Project1人1人の飾らない人柄だったように思う。彼らが、『SKILL』を超える楽曲を生み出すのかはもちろんのこと、これからもアニソン界にどんな化学変化や光を与えてくれるのか楽しみだ。
ドキュメンタリー映画『GET OVER -JAM Project THE MOVIE-』は2月26日より2週間限定公開予定!