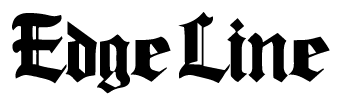俳優で歌手・生田絵梨花が9月20日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで全国ツアー『Erika Ikuta Tour 2024 「capriccioso」』ファイナル公演を開催し、無事ツアーを完走した。
ツアーは今年は7月に埼玉・愛知・大阪、8月には宮城・東京と、今回のファイナルを含めて6都市7公演で開催。のべ1万7000人を動員した。
以下、公式レポート部分。
2022年夏に音楽活動を始動して以来、4月には約2年越しのデビュー作としてEP『capriccioso』を発表。今回のライブテーマ、そしてタイトルにも冠した“capriccioso”の意味は、音楽用語で気ままに、気まぐれにーーそれは言い換えれば、自身のペースで音楽活動を続けていく、といったさりげない意志表示、あるいは願いなのかもしれない。
『capriccioso』を軸として、これまで以上に自身の色を表出しながらも、世界観はあえてがちがちに決めきらず。どこか緩く、遊びの部分を残していたあたりに、いかにも彼女らしさを感じたステージの模様を振り返っていこう。
幕開けは、EPのリード曲「Laundry」から。生田が自宅で洗濯機を回しているとき、ふと思いついた鼻歌から生まれたこの名曲。トリッキーなテンポの歌い出しや、藤井 風リスペクトを感じるジャジーなサウンドで、独特かつ心地よいグルーブ感を構築していくと、序盤の〈あぁもう 嫌んなっちゃうよ〉では客席の方を向いて、左目を大きくウインク。ここからの夜が最高なものになると約束する。そんな合図にも思えた。
すぐに日常を忘れさせることはないーー日常と地続きで、その香りを残しつつ、肩の力が抜けるサウンドを大切にしながら、最後には加速した水が洗濯機から排水溝へと“ぐんっ”と流れていくように。演奏終盤は一気に勢いを乗せて、生田の歌の世界に引き込まれる。
続く「I’m gonna beat you!!」も、生田自身で作詞作曲を手がけた楽曲。こちらは音源の段階からすでに、生田の歌声が身を乗り出してくる、むしろライブに近い歌い方に痺れていたのだが、生の現場ではさらに動きの躍動感も追加。ピアノソロは、“前ノリ”で首と肩を大きく揺らす。好きな相手を前にして、身体が気持ちに追いつかないかのように……歌、ピアノ、バイブスと、やることたくさんな生田が大サビにて、よい意味で打鍵に詰まりかけていたあたり、楽曲に込めた想いを体現している気がした。最後は“もう耐えられん”と言わんばかりに、ピアノから豪快に腕を払ったのも解釈一致でしかない。
そこから、EP収録の藤井風「ガーデン」、森山直太朗「花」を続けて歌唱。「ガーデン」では、声のエッジを柔らかくくぐもらせ、湿度の高い雰囲気に。この楽曲は高揚感への導き方が素晴らしく、前半は白昼夢を見るかのような浮遊感に包まれていたのだが、大サビ前のブリッジからは、生田がピアノから手を離し、何層にもフェイクを重ねて、力のこもった歌い方を見せる。それとは対照的に「花」では終始、笑顔よりむしろ、時代を想う表情すら見せながら、今度は声の輪郭を明瞭に聴かせて、儚げなファルセットを挟む場面も。同じ“花”をモチーフとしながら、たった2曲でこれほどのコントラストを際立たせられるとは。
そんな感動を運びながら、密かに“あること”が気がかりだったという生田。たしかに先ほどの演奏中も“ん?”と顔に出ている時間があったのだが、実は冒頭のMCにて、この日がツアーファイナルであることに触れ忘れていたのだとか。曰く、客席のサイリウムのリズムから「ファ・イナル! ファ・イナル!」と邪念……ではなく、ツッコミの念が届いてきたとのこと。「やってもうたわ!」と笑い飛ばす抜けっぷりを目撃して、直前まで「ガーデン」「花」を見事なまでに歌い上げていたのと同一人物なのか? そう疑いたくなってしまったが、客席はこの後、各々のタイミングながら、少なく見積もっても3回はこうした気持ちにさせられる場面に遭遇していたと思う。
ライブ後半のハイライトは、“懐かしの夏ソングメドレー”。アイドル時代は定番だった「いくちゃーん!」のお名前コールを久しぶりに浴びて、ご満悦になったピンク・レディー「渚のシンドバッド」を皮切りに、“ありがとう”の声にも妙にダンディさが乗り移ったRATS&STAR「め組のひと」を経由し、“シンドバット”挟みで、最後はサザンオールスターズ「勝手にシンドバッド」で茅ヶ崎のビーチに強制連行。日本人のDNAに刷り込まれた〈la la la〉のコーラスで、会場の熱量も一気に頂点へと達した。もちろん、件のコーラスが完璧だったのは言うまでもないし、この後、めちゃくちゃタオルも回した。
さらに、YOASOBI「アイドル」もカバー。ボーカルパフォーマンスだけでも運動量は充分なほどだが、途中までダンスをしていたかと思えば、まさかの落ちサビからはグランドピアノの前に舞い戻り、ラストはダイナミックに立ち弾きまで。もはや、J-POPトライアスロン。言わずもがな、本人は満身創痍なはずだし、その様子も微かに伝わってくるのだが、決して息は上げない。
自身を追い込むラストスパートに、“アイドルは常に笑顔でいる”と歌う楽曲を置いてきた意味。この配置に、客席全体も単にカバーするだけでは終わらせないという並々ならぬ想いを感じ取ったのだろう。生田が後に「陸で溺れるって思ったのは初めて」と振り返ったほど、曲中はファンの声援が鳴りやむことなく、むしろその大きさは右肩上がりだった。
本編最後を飾ったのは、EP収録曲で唯一、このツアーが初パフォーマンスとなった「だからね」。柳沢亮太(SUPER BEAVER)から提供されたこの楽曲は、生田にとって自作曲の“原点”にあたり、アンコールで披露した「No one compares」からさらに深化した、彼女の本心にさらに踏み込んだ大切な一曲である。
あなたが一人でいるとき、いまとは違う顔を持っているかもしれない。なにか抱えていたり、悲しみを感じているかもしれない。それでも、私はその顔までは見にいくことはできないし、見にいくわけにはいかない。だが、そんなときにふと、今日の思い出が心に浮かんできたり、音楽という形にこだわらずとも、外に出かけてみようなど、なにかのきっかけになれていたりしたらうれしい。歌唱前のMCでは、そんなことが語られた。こうして言葉にした方が明確に伝わるはずなのに、歌とは不思議なもの。この後の「だからね」の5分間には、同じメッセージが言葉で並べるよりも強く、ぬくもりと共に詰まっている気がした。
そのほか、本編の詳細をいくつか割愛したのだが、約4年ぶりに手にしたアコースティックギターで弾き語りをしたハマいく「ビートDEトーヒ」や、腰回りを強調した激しいダンスをはじめ、ボイスチョップからいわゆるヒップホップの“アドリブ”まで、通常は音源で補完するところまで生歌唱し、もはや“一人MAMAMOO状態”にまで上り詰めた「HIP」といった驚くばかりの見どころも。また、自身に縁ある作品としてディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』より「ようこそ!ロサス王国へ」など豪華3曲のほか、アンコールでは今年12月より上演となる舞台『レ・ミゼラブル』より「夢やぶれて」なども披露するなど、本編を終えてもなおサプライズな展開続きとなった。
とはいえ、まだ終わらない。ファイナル公演のみ特別に、新曲「シンフォニー」を初披露。生田は今回、作詞のみを手がけており、本ツアーを通してバンドメンバー、そして応援してくれるファンの一人ひとりと向き合うなかで生まれた言葉を歌詞にしたという。
ピアノがメロディを牽引するミニマルなピアノポップスだが、大袈裟な飾り付けはなくも、バラードほどシンプルではなく。“シンフォニー”というタイトルは、それぞれが持つ個性や人生の歩みこそ違えど、ぬくもりを渡し合うーーまさにこの空間を喩えたもので、曲中の〈いつかきっとまた会える/交わした眼差し 約束するように 手を振って〉は、誇張抜きに目の前に広がる光景をリアルタイムで当て書きしているようだった。
ラストナンバーは、始まりの楽曲「No one compares」。1コーラス目をピアノ一本弾きで歌唱したところで、この2時間で何度も目にした姿ながら、ここまでで彼女が最も近い距離に居てくれるようなーーまるで、隣で語りかけてくれている感覚を抱いてしまった。が、それは決して錯覚などではない。会場に集まったファンもきっと同様だったはずだし、そう感じられたということは、彼女の想いが全19曲を通して、しっかりと伝わりきったという証拠にほかならない。
生田絵梨花という人を語るとき、いわゆる才能の“マルチ”な側面が押し出されがちだが、彼女は第一にやはり、音楽の人。さまざまな解釈があってよいものだが、ほか歌手の楽曲カバーをするのみでなく、自分だけの音楽を体現し、歌として表現するソロアーティスト活動の意味は、本人のパーソナリティや人生が歌詞の一言一句に重なるところにあるのではないだろうか。その点において、最後に披露された新曲「シンフォニー」が生まれたことで、生田の音楽活動を徐々に明確かつ強固に。そして、この心地よい空間にも、どこか名前をつけてもらえたような感触を覚えた。
新曲が生まれたということは、次のライブも待っているはず。このツアーのゴールテープを切り、生田絵梨花はまた新たなスタートラインに辿り着いた。これからもきっと、気ままに、気まぐれにーー自分のペースを保ちながら、次の楽譜をめくっていくのだと信じたい。
ライター 一条皓太