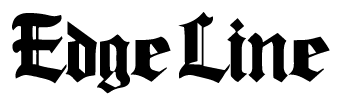俳優・中村倫也(32)が7日、都内ホテルで『2019年 第43回 エランドール賞』表彰式に登場した。
エランドール賞は、1956年に日本映画テレビプロデューサー協会が制定した賞。新人賞は日本国内において当該年度中の12月1日から翌年11月30日までの間に、上映または放映されたテレビドラマ作品に出演した俳優であることや、出演した作品で新鮮かつ優秀な演技をした者などが選出されている。中村は志尊淳、葵わかな、田中圭、永野芽郁、松岡茉優とともに新人賞を受賞したことから登壇となった。
壇上ではトロフィーを掲げたりとお茶目な一面を見せていた中村がスピーチをはじめた。以下、全文。
「こんな素敵な身に余る賞を頂いて、恐悦至極に存じております……難しい言葉を使いました、中村倫也です(笑)。こうしてトロフィーを頂くとうちのシャイな両親がバカみたいに喜びます。親孝行させて頂いてありがとうございます(観客達から拍手が起こる)。こんな素敵な賞を僕みたいな人間がもらって、何ができるのかなと考えながら、きょうここまで来ました。思い返すと17歳の夏に映画『七人の弔』という映画でデビューさせて頂きまして、はや15年ほどになるんですけれども、長い長い道のりでした。きょうこうして、ここで喋らせてもらうということも……長い長い道のりでした。
その道のりの中で、何度も壁に直面し、挫折を味わい、本当に自分の才能の無さとかに打ちひしがれ、悩みながらここまで来たんです。そんなとき、いつも考えていたのがある先輩の言葉で、『お前は何になりたくて、どうしたいんだ?』と、あるとき言われたんです。それを悩むたびに自問自答しながら考えて、いつも導き出させる答えは、僕はこの仕事が好きで、少しでも良い芝居をして、少しでも良い作品を作って、観てくれるお客さんの人生が豊かになるような、考える機会になるような、元気が出るような、そういう追体験をしてもらいたい。いつもその答えでした。
そんなふうに胸の中の炎が消えかかるたびに、自問自答して、また薪をくべて、たくさんの素敵な出会いに支えられて、いまこの場に立てています。なので、きょうは若い方も多いでしょうし、僕のしゃべっていることを観た人が、やりたいこと、叶えたいこと、追いかけていること、それに対して炎が消えかけている人がいるとしたら、僕みたいな人がこの場所に立てているということが、その人にとっての薪であり、燃焼剤であり、何かになればいいなと思って、いまここでしゃべっています。
賞というものはですね、言葉を置き換えると、責任だと考えています。さっき、(志尊)淳も言っていたことです。きょうからまた、靴紐を結び直して、あの頃のようにしっかり自問自答しながら信頼できるマネージャーと二人三脚で、虚心坦懐(きょしんたんかい)な心持ちを忘れずに(笑)。また、難しい言葉を使いましたね(笑)。少しでもたくさんおもしろい作品を作って、みなさんに観てもらえるように頑張っていこうと思います。本日はありがとうございました」
約3分にわたり思いを語り続けた中村。その直後には、事務所の後輩の菅田将暉が花束プレゼンターとして「急に登場してすいません」と、現れることに。
中村の受賞へ菅田は「本当に嬉しいです。自分ごとのように嬉しいです!中村倫也さんは僕の本当に大好きな、尊敬している先輩で、そんな方の晴れやかな日に立ちあえたことが嬉しいです。何回も倫也さんに救って頂いたことがありました」と、万感といった様子。
今回登壇したのは、「後輩でちょっとぐらい名前の知られているお前が行って来いと言われたわけではなく、自分の意思で来ました。ずっと、個人的にこんなに巧みで、バラエティーに富んでいて、こんなに格好いい人がいるのに、なんでみんな見てくれないのかな。もっとみんな見てくれよ!と、思ってました。だから、本当に嬉しいんです」と、気持ちが先に立ったのだとか。そんな真面目に語る横で、中村は菅田ににじり寄る姿を見せ、2人の関係性がわかるような一幕に、温かな笑い声も挙がっていた。
ちなみに中村は菅田の登壇は知らず、「去年受賞したムロツヨシというおじさんがいるんですが、やたら『スピーチ頑張れ!』って7件メールが来まして、頭の中が完全にそうなってました(笑)」と、ムロからの口酸っぱいほどのアドバイスあっての“仕込み”だったことも話しつつ「違う種類のパーマが来ましたね」と、菅田とこの場にいないムロへ同時にツッコミをいれ場内は爆笑だった。
その後、囲み会見では菅田の登場へ「すごい嬉しかったです。事務所に入ってきたときから、こいつは絶対大物になるなと思っていて、大物になったときにおごってもらおうと思って仲良くしようと思って」と、“打算”があったことを告白しつつ、「でも僕の好きなやつで嬉しかったんですけど、先輩のことをしゃべるので、気を使わせてしまったかなって。嬉しいのと照れくさいのという感じがありました」と、ここでもさりげなく気遣いを見せていた。